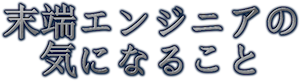【IT業界だけ?】非エンジニアの皆さんに知ってほしい2つの目線
2016/06/16
IT業界に身を置いてない人に知っておいて欲しい考え方だなと思ったので記事を書きました。
だらだら長いですがお付き合い下さい。
目次
最初にこれを読んでみて下さい。
まずは、元々のインタビュー記事を読んでほしいです。ここに全て引用してしまうとHRナビさんの記事の価値がなくなってしますので、冒頭のみ引用させて頂きます。
「できます=やります」じゃない、知ってほしいエンジニアのこと
今回は、非エンジニアとエンジニアの距離を縮めることを目的に、エンジニア目線で「エンジニアが困る仕事の頼み方」や「エンジニア独特のコミュニケーション文化」について語ってもらいました。エンジニアと非エンジニアで大きく文化が異なるポイントは、いくつかあると思います。真っ先に思い当たるのは、「言葉のニュアンスの違い」です。
via HRナビ.com
目線1. 「動かなくなった」と言われても、エンジニアは動けない
仕事の依頼については「要件定義」をハッキリしてほしいんですよね。「こういうものを作りたい」「こういう問題を解決したい」というゴールが明確でないと、最終的なアウトプットがズレてしまうことは、往々にしてあります。
via HRナビ.com
これは共感できます。このフレーズを聞いても何をして欲しいのかわかりません。
動かなくなったからどこを治してほしいの?
動かなくなったから何の原因が知りたいの?
動かなくなったから別のに乗り換えたいの?
なんて考えていてもわからないので、結局ヒアリングすることになります。
そこでもあいまいな答えが返ってくることがある。
この業界は、あいまいな依頼ではエンジニアは動けないのです。
自動車を治すにしても要素がたくさんあります。エンジン、ブレーキ、冷却循環・・・etc
要素ごとに必要な器具、修理の方法が全然違ってきます。どれを準備したら良いのでしょうか。
各要素が今どうなっているのか、どう良くしたいのか、
全部ヒアリングするところから始めないとダメなんでしょうか。

依頼する側すれば、具体的なことはエンジニアが調べ・考えるべきことだと思うのは当然です。
ですが、エンジニアは問題に対して"アクションして解決をする"を繰り返しているのです。
エンジニアは最適な修理方法を考えて問題を解決するのが役割であって、
修理でどう良くしたいのかを決める役割ではないはずです。
また、立派な自動車の写真集を見て、こういう風には作れないの?と質問が飛ぶことがありますが

物理的には作れます。被写体として存在しているのだから。
でも現実的には作れない。正確な見積が作れませんからね。
実際に完成させるところまでいかないと正確な見積は出せないです。
もちろん先行して作ることはできません。後で発注した覚えは無いって言われたらビジネスとして赤字ですから笑
だから『できる=やれる』ではないと思います。
目線2. 急用以外は、チャットでお願いします
たとえ社内で目の前に座っている人が相手だとしても、急用でなければ基本的にチャットなどの「非同期コミュニケーション」にしてほしいと思っています。
via HRナビ.com
これにも共感します。
僕の勝手かもしれませんが、即答を求められるコミニュケーションは避けたいです。
細かい作業をしているときの電話や話しかけられることですね。
手が空いてればOKですが、作業に集中しているときに即答を求められるとつらいです。

何がつらいのかと言うと、具体的なアクションで説明します。
- 手を止めて今まで考えていたことを記録。会話中に忘れてしまいますからね。
- 相手の話を聞き、答えを考え返答する。
- さっきの記録を元に作業を再開。記録が正確であることを祈りつつ。
これが精神的負荷が大きくてつらい。怒られるよりつらい。
メールやチャットであれば、内容を見てから即答すべきか、後で返答すべきか自分で判断できます。
一番幸せなのはメール見たら電話下さい的なやつですね笑。これ最高。
緊急でなければメールやチャットなどの『非同期コミュニケーション』を積極的に使って欲しいと思います。